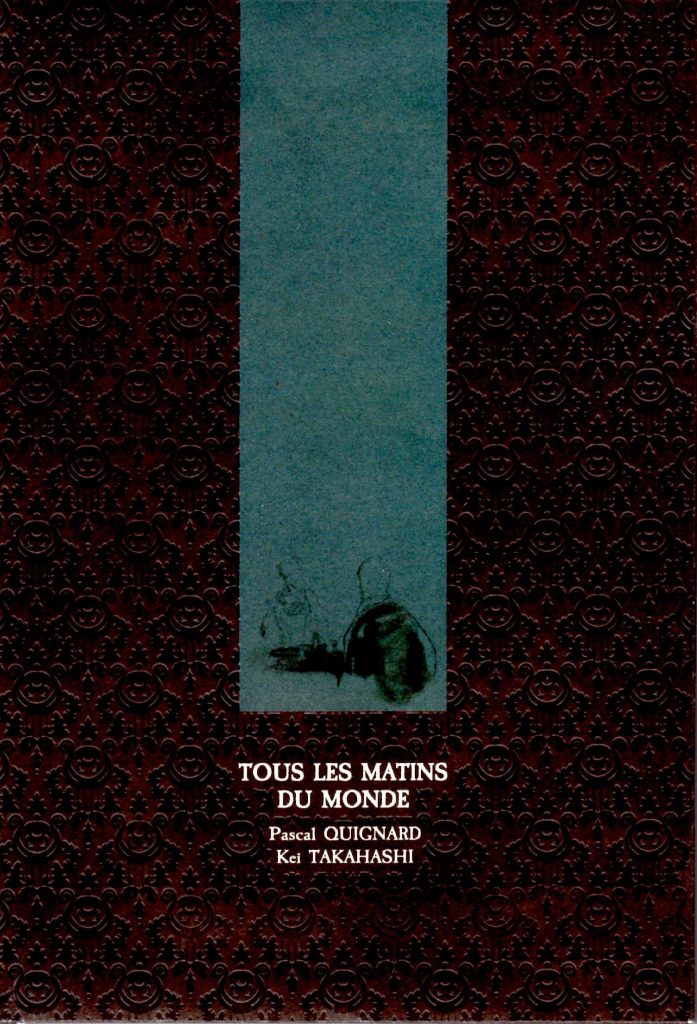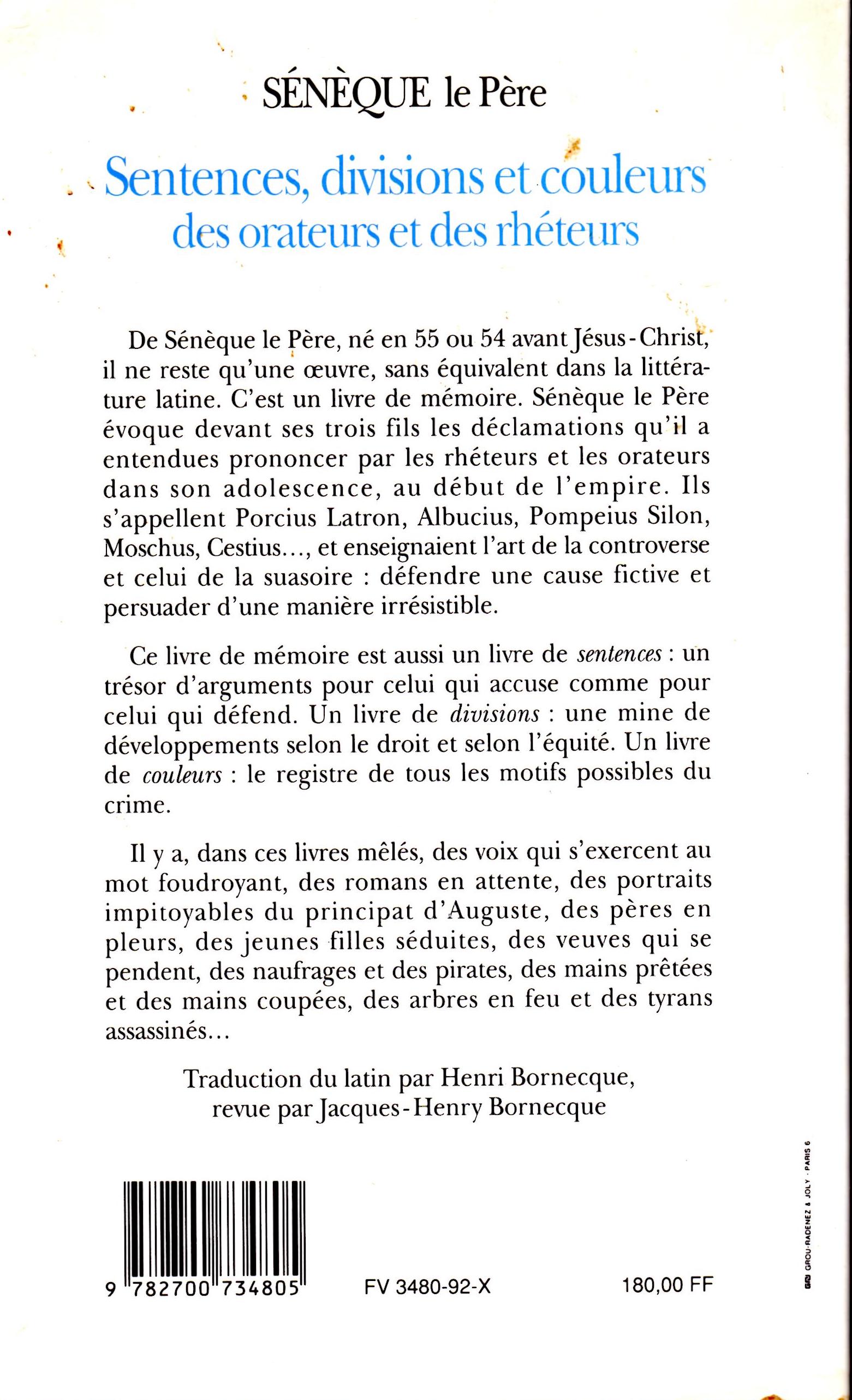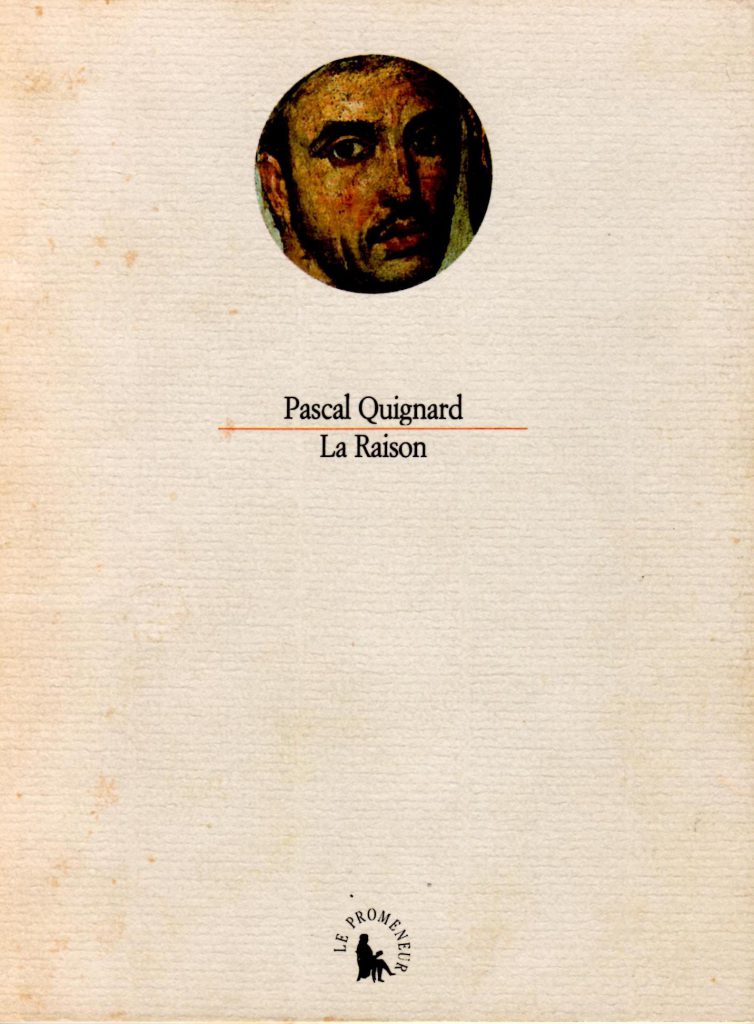Postface du traducteur
(Traduction par Déborah Pierret Watanabe)
Tous les matins du monde (Gallimard, 1991) de Pascal Quignard, fait l’objet d’une nouvelle publication chez Kajikasha, maison d’édition limitée au Kyushu et dont le siège se situe à Kumamoto. Je vais d’abord vous expliquer comment nous avons pu en arriver là.
La première traduction de cette œuvre est parue chez Hayakawa Publishing en 1992 sous le titre Meguriau asa. Comme le projet avait été de s’associer au film réalisé par Alain Corneau, le titre du livre avait été choisi en fonction de celui du film sorti au Japon.
Vingt-cinq années se sont écoulées depuis. Je me permets ici d’exprimer mon émotion, car jamais je n’aurais osé imaginer, pas même en rêve, qu’une œuvre de ce genre puisse à nouveau être publiée.
Il était fondamentalement impossible que le roman, destiné à être le scénario d’un film, puisse paraître une nouvelle fois, alors même que le film ne faisait pas l’objet de nouvelles projections.
Ce qui permit de rendre cet impossible possible fut la détermination de Yô Kaji, représentant de Kajikasha. Tout comme elle avait d’ailleurs permis la nouvelle publication du Voyage d’Hector ou la recherche du bonheur de François Lelord, fin 2015.
En mars 2016, après la sortie du Voyage d’Hector, Yô Kaji m’a invité à venir lui rendre visite dans le Kyushu. Je suis allé à Kumamoto, Hakata, ou encore Hita pour participer à des rencontres littéraires dans le cadre de la promotion du livre. Malheureusement, le 14 du mois suivant, la terre de Kumamoto a été ébranlée par un violent séisme. C’était plus fort que moi, il fallait que j’y retourne.
J’ignore à quel moment, mais, au cours d’une de nos discussions, Yô Kaji et moi-même avons eu l’idée de proposer Tous les matins du monde en tant que nouveau projet de publication chez Kajikasha.
À mes yeux, ce roman représentait le souvenir du début de ma relation avec l’auteur. Mais il était également ma pierre d’achoppement. Même la postface que j’avais rédigée pour la première publication ne me plaisait pas.
Je crois bien m’être laissé emporter et avoir fini par m’éloigner du chemin du devoir du traducteur, cet homme de l’ombre. Je n’ai pu, pendant de longues années, réussir à relire cette traduction.
Néanmoins, l’impression de Yô Kaji était tout autre. Il m’a confié que c’était justement grâce à cette traduction et à ma postface qu’il avait pu être entrainé dans le monde littéraire de Quignard.
J’étais stupéfait. Il m’a dit vouloir conserver le texte que j’avais écrit il y a vingt-cinq années de cela alors que je n’étais encore qu’un quadragénaire. L’idée que ce texte puisse à nouveau être révélé au grand jour, moi qui l’avais enfermé au grenier sans jamais oser y reposer les yeux dessus, me paraissait effrayante.
Les textes que j’ai écrits et qui ont été publiés ne m’appartiennent plus, ai-je cependant songé. Si l’un d’entre eux continue de vivre dans le cœur de quelqu’un, alors je n’ai pas d’autres choix que de me résigner.
J’ai donc à nouveau traduit cette œuvre et décidé de conserver la postface de la première publication. En revanche, j’ai coupé et abandonné les parties qui avaient vieilli et n’avaient désormais plus de sens pour ne laisser que celles indispensables à la lecture de ce livre. J’ai également profité de cette nouvelle édition pour insérer d’autres citations ainsi que de nouvelles anecdotes.
*
« J’ai lu l’histoire de monsieur de Sainte Colombe tout en ayant l’image de mon grand-père à l’esprit », avais-je impudemment écrit lors de la première postface. Il y avait une raison à cela. Je n’avais aucune envie de limiter les lecteurs de ce livre qui a pour cadre le lointain XVIIe siècle aux étudiants de Lettres et à leur entourage. Je voulais en faire un livre également ouvert à toutes les personnes sans lien particulier avec l’histoire ou la littérature qui étaient venues voir le film. Mais en réalité, ce n’était pas seulement cela.
Avec la ferme intention de lui faire rencontrer au Japon le succès que cette œuvre avait connu ailleurs, je me suis envolé pour Paris au début de l’été 1992. Je suis allé rendre visite à l’auteur — qui était alors encore en poste chez Gallimard — en emportant avec moi une petite photo encadrée de mon défunt grand-père. Je ne me rappelle plus vraiment comment nous en sommes arrivés à avoir cette discussion, mais toujours est-il que j’ai fini par lui montrer la photo.
— Mon grand-père est mort sans rien laisser derrière lui, lui ai-je dit.
Ce à quoi il a répondu :
— C’est faux. Ne t’a-t-il pas laissé, toi ?
Nos mots, tout comme lors du dernier échange entre Marin Marais et Sainte Colombe, n’avaient fait que se croiser. Cependant, à ce moment, il y eut comme une sorte de communion entre nous (du moins, c’est ce que je crois.)
Mon grand-père est décédé au cours de la dernière année de mes études universitaires. Il avait 84 ans. Allongé sur son lit de mort, il a trempé ses lèvres dans un petit bol d’alcool puis il a quitté notre monde. Je n’ai pas assisté à sa mort, mais je me suis rendu à ses funérailles. J’ai toujours pensé que ça avait été une mort parfaite. J’ai écrit ceci dans la première postface : « Il élevait chevaux, porcs, moutons, poulets, et tout comme monsieur de Sainte Colombe, il vivait dans une petite cabane dans la cour dans laquelle il avait installé son lit, et ce, même s’il avait sa chambre dans la maison. Lorsque j’étais enfant, j’aimais dormir avec lui dans ce lit de fortune. Je me souviens, même encore maintenant, du vert délavé des rigides draps de chanvre et de la fenêtre aux vitres givrées ».
Les funérailles de mon grand-père se sont achevées, une nouvelle année est arrivée, et je suis rentré à Tokyo. Le moment d’être diplômé était venu, mais je m’interrogeais toujours sur la façon d’établir un point de contact avec la société. J’étais incapable de me projeter dans l’avenir. De plus, je n’avais ni le désir ni la volonté de rester à l’université. Un jour de janvier, alors que la nuit était déjà bien avancée, un ami est venu me rendre visite, avec, comme à son habitude, une bouteille de whisky bon marché à la main. Lui non plus n’arrivait pas à se projeter dans l’avenir. Mais sa visite n’avait pas été motivée par le besoin de parler du futur. Plutôt pour débattre de littérature. Dostoïevski, Kierkegaard, Pascal… Oui, la flamme de l’existentialisme n’était pas encore tout à fait éteinte. Parmi les hommes de lettres japonais, mon ami avait une préférence pour Hideo Kobayashi et Shun Akiyama.
Je me suis endormi le premier. Quand j’ai ouvert les yeux, au point du jour, il avait disparu. Un ou deux mois plus tard, j’ai reçu un faire-part de décès. Son corps sans vie avait été retrouvé sur les quais de Shinagawa. Il s’était noyé.
C’était un garçon originaire de Fukushima. Je fus le seul de notre promotion à me rendre à ses obsèques. Son père, maître du cortège funéraire, fit une déclaration : « On pourrait penser qu’un fils qui part avant ses parents est ingrat, mais je ne suis pas de cet avis. » À cet instant, un sentiment mystérieux et féroce, à la fois colère, à la fois tristesse, envahit tout mon être. Je le réprimai de toutes mes forces. Le lendemain, son père a eu la gentillesse de me faire visiter Fukushima en voiture. J’ai alors pensé que je devais trouver un travail, peu importe où.
Ces deux morts auxquelles j’ai été confronté avant même d’être entré dans le monde ont par la suite régné sur ma vie. Ce que j’avais voulu transmettre à P. Quignard ne concernait peut-être pas mon grand-père. Peut-être que cela concernait mon défunt ami.
*
Ce roman regorge des regrets envers les petites choses qui ne sont que des détails ou des anecdotes si on les regarde du point de vue du courant de la grande Histoire. Le choix du musicien Sainte Colombe en tant que personnage principal est déjà révélateur. Ce nom n’évoque absolument rien aux non-connaisseurs de musique baroque. Même ses dates de naissance et de décès demeurent floues, on sait simplement qu’il est mort vers 1700. Ou encore cet instrument de musique, la viole de gambe, qui a connu son heure de gloire sous le règne de Louis XIV pour ensuite tomber dans l’oubli. L’abbaye de Port-Royal dans la vallée de Chevreuse, siège des jansénistes également appelés les Solitaires, rasée par la poudre sur ordre de Louis XIV ; les petites écoles rue Saint-Dominique d’enfer à Paris ; les gaufrettes de Baugin, peintre que l’on peut qualifier d’anonyme comparé à Poussin ou à Champaigne de la même époque… Tous les personnages de ce roman sont des Solitaires. Les solitaires éternels de l’Histoire. Mais face au courant de la grande Histoire, je ne peux s’empêcher de penser que tout le monde l’est plus ou moins.
Le problème est la houle de cette grande Histoire, la houle qui a englouti tous les solitaires. Depuis le Moyen Âge jusqu’à la Renaissance, de la naissance du baroque à sa fin. Cette houle coule en arrière-plan du roman. Il ne fait aucun doute que le baroque, tout en étant illuminé par la splendeur de la Renaissance, regorgeait des souvenirs sombres et envoûtants du Moyen Âge. Au chapitre IX de La Sorcière, intitulé « Satan triomphe au XVIIe siècle », Michelet écrit ceci :
Plus sa surface, ses couches supérieures, furent civilisées, éclairées, inondées de lumière, plus hermétiquement se ferma au-dessous la vaste région du monde ecclésiastique, du couvent, des femmes crédules, maladives et prêtes à tout croire.
Les propos de Michelet décrivent bien les deux tendances contradictoires inhérentes au baroque : celle qui aspire à un espace plus grand et plus ouvert, et celle qui prétend à un espace plus fermé et intime. D’un côté, nous avons l’Opéra qui s’est développé en Italie, la majestueuse Passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach, la splendide musique de cour de Lully, et de l’autre des pièces instrumentales diverses et variées qui cherchent à imiter les inflexions de la voix humaine ou encore la tiédeur de la peau. De même, nous avons l’architecture baroque de Rome qui use et abuse de la perspective à un point tel que l’espace ou encore les peintures sur plafond sont pareilles à des dinosaures colossaux, mais aussi les natures mortes d’Espagne ou les scènes d’intérieur du Hollandais Vermeer, la lueur froide des chandelles de Georges de La Tour. Tous partagent comme point commun une atmosphère de densité de la matière.
De même, la politique d’expansion des cartes du royaume, à mettre en parallèle avec la politique d’évangélisation des jésuites à un niveau mondial ou encore la vulgarisation de la religion contrastaient voire même s’opposaient au rigorisme et à l’élitisme des jansénistes. Si je devais m’exprimer à la manière de Michelet, je serais tenté de dire qu’il y avait là une sorte d’ambivalence, un conflit entre l’ivresse et l’angoisse envers l’appel de Satan au nom de la rationalité.
Il vaudrait tout de même mieux se pencher plus sérieusement sur la période du XVIIe siècle en France. Louis XIV accéda au trône en 1643, mais son règne ne débuta qu’en 1661, date à laquelle le cours de l’Histoire a basculé. Dans son Histoire de la Civilisation française, écrite avec la collaboration de Georges Duby, Robert Mandrou estime que la période entre 1600 et 1660 est celle où la France moderne s’est « faite » et la désigne sous le terme « adolescence » :
Cette adolescence est terriblement conquérante, au milieu des drames sociaux et religieux qu’elle a vécus et qui sont sa crise de croissance. À tous égards, c’est le XVIIe siècle le plus riche, le plus vivant.
Le roman débute en 1650 à la mort de l’épouse de monsieur de Sainte Colombe. En d’autres termes, l’histoire commence à la fin annoncée de l’adolescence de la France. De plus, il ne fait aucun doute que l’auteur fait un parallèle entre la mort de la femme du musicien et la fin proche du baroque.
Pourquoi monsieur de sainte Colombe refusait-il d’aller à Versailles avec tant d’entêtement ?
Dans l’imagination de l’auteur, le musicien était le condisciple de Claude Lancelot, corédacteur de la révolutionnaire Grammaire générale et raisonnée avec A. Arnauld, leader de Port-Royal. Cependant, si on lit attentivement l’œuvre, il n’est à aucun moment décrit comme un janséniste fanatique. Il est simplement suggéré que ses relations se limitent aux lieux éloignés du pouvoir, comme le poète Vauquelin des Yveteaux (1567-1649) qui avait perdu les faveurs du roi louis XIII à cause de sa nature libertine ou encore Baugin (1612-1663), simple artiste appartenant à la corporation des peintres parisiens. Madeleine, quant à elle, connut une période de fanatisme causée par son chagrin d’amour, mais refusa d’entrer au couvent. Père et fille sont isolés. Ils se referment volontairement sur eux-mêmes. Peu importe l’époque, lorsque le courant de l’Histoire vire brutalement, il y a ceux qui opposent une violente résistance au point d’en être imprudents et ceux qui s’obstinent à se renfermer sur eux-mêmes. Cette époque, cette obstination, ce rigorisme m’évoquent nécessairement Blaise Pascal.
En novembre 1654, à l’âge de 31 ans, Blaise Pascal éprouva une expérience mystique à cause de laquelle il abandonna tous les travaux scientifiques qu’il avait réalisés jusqu’alors pour entrer à Port-Royal. Cette nuit de novembre, il coucha sur un parchemin un texte intitulé Mémorial dans lequel il parle d’une « une renonciation totale et douce ». Blaise Pascal prit ensuite faits et causes pour Arnauld — auteur de De la fréquente communion, au cœur d’un débat lancés par les Jésuites et la Sorbonne —, devint une figure de la défense des jansénistes, et commença à rédiger les Provinciales, une série de lettres de protestations. Ses attaques vont finir par se diriger vers Descartes et son travail, qu’il qualifiera même d’« inutile et incertain ».
Qu’a t-il bien pu arriver à Pascal ? Ce n’est pas le lieu approprié pour en débattre et je n’en ai pas les compétences. Mais il me semble important d’ajouter que les jésuites et la Sorbonne n’ont cessé d’intensifier leurs attaques envers l’école cartésienne après le décès de Descartes en 1650, lui qui disait répugner à déranger l’opinion publique. C’était une époque où, au nom de la France et de la monarchie des Bourbons, tout était unifié et destiné à être intégré. Ce fut la même chose pour le courant des Beaux-Arts en Europe, de David à Delacroix, de Haydn et Mozart à Beethoven, du Classicisme au Romantisme. Les grandes vagues ont englouti les petites. Les grandioses peintures historiques et symphonies sont pareilles aux armées puissantes des états modernes. Elles mobilisent toutes les sensibilités et les écrasent. Du point de vue de la formation de cet état moderne, à la fois nationaliste et industrialiste, les époques qui ont suivies, de Louis XIV à Robespierre jusqu’à Napoléon, sont des plus cohérentes, et la Révolution française n’a finalement été qu’un feu d’artifice parmi les grandes émeutes. Les innombrables petits matins qui gardaient encore le goût envoûtant du Moyen Âge, les matins que les libertins et les cosmopolites ont admirés lors de leurs voyages, ont été anéantis par la sirène du puissant état. Ce n’est sûrement pas qu’une vieille légende limitée à l’Europe.
La période baroque comportait en son sein des contradictions à jamais inconciliables.
Près de trois siècles s’étaient écoulées depuis Descartes et Pascal, quand Paul Valéry railla ce dernier à propos d’un extrait de ses Pensées : « le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie », écrivant qu’il lui faisait songer à « cet aboi insupportable qu’adressent les chiens à la lune ». Face à l’infinité de l’univers, ressent-on l’ivresse ? Ou au contraire, se sent-on effrayé, prend-on conscience de notre qualité de pécheur ? Tout cela me paraît être, même encore maintenant, une opposition fondamentale entre la sensibilité et ce que doit être la pensée.
On peut également citer Matisse à titre d’exemple. Il détestait le baroque, a déclaré que « Vélasquez n’était pas son peintre » et aimait parler de l’affection qu’il portait à Goya. Matisse qui préférait peindre le coin d’une pièce. Cet espace qui ne s’étend nulle part. Juste l’apaisement des couleurs authentiques. Question mystère, les peintures de Baugin ne sont pas en reste non plus. La composition de ses tableaux suggère le caractère éphémère des plaisirs d’ici-bas. Mais pourquoi avoir choisi de peindre des coins de table ? Et monsieur de Sainte Colombe, à la recherche des inflexions délicates de la voix humaine, tentant de faire venir des airs mélancoliques, des airs de regrets sous ses doigts…
Il y a là un chemin extrêmement étroit par lequel passe la beauté pour atteindre le monde des prières. Pascal Quignard a fait dire au peintre Baugin : « Personnellement je cherche la route qui mène jusqu’aux feux mystérieux. » Ces mots sont aussi ceux de l’auteur amateur de Georges de la Tour.
(Extrait du posteface du traducteur dans la première publication de la version japonaise.)
*
Pascal Quignard, écrivain français ne cesse de réfléchir à l’essence de la musique, a écrit dans la Haine de la musique (Calmann-Levy, 1996) :
Les dieux ne se voient pas, mais s’entendent : dans le tonnerre, dans le torrent, dans la nuée, dans la mer. Ils sont comme des voix. L’arc est doué d’une forme de parole, dans la distance, l’invisibilité et l’air. La voix est d’abord celle de la corde qui vibre avant que l’instrument soit divisé et instrumenté en musique, en chasse, en guerre.
Dans Tous les matins du monde, Pascal Quignard a réécrit l’histoire de Semimaru du Konjaku monogatari, pour la situer en France, au Moyen Âge. Et pour moi, Japonaise, ce fut une expérience très intéressante. Je suis allée voir le film en compagnie de Bernard Frank, traducteur français des Histoires qui sont maintenant du passé, tirées du Konjaku monogatari. C’est à ce moment que Bernard me fit remarquer d’un air heureux que les deux histoires étaient similaires. Une fois rentrés, je me suis empressée de vérifier ses dires, et effectivement, l’histoire du film était similaire à celle de Semimaru.
« La magie des sons » extrait du dernier recueil d’essais de Yuko Tsushima.
*
Bach a échoué. Il a été oublié pendant un long moment. La musique n’a pas avancé dans sa direction. Si, à l’heure actuelle, tout le monde cherche à trouver de nouvelles significations à sa musique, c’est parce que la musique est sur le point de changer. La musique est abstraite, et en allant trop loin dans une direction, il arrive qu’elle finisse par être coupée de l’ensemble. La musique européenne s’est développée à l’extrême, le moment de changer de direction est venu. Le style s’adapte à l’époque, mais ce qui est encore vivant se trouve sous le style. C’est la qualité, c’est l’attitude.
« Bach a échoué » extrait du recueil d’essais de Yuji Takahashi, musicien.
*
Un quart de siècle s’est écoulé. Cela peut paraître bien long, mais c’est comme si c’était hier. Pascal Quignard qui a écrit dans ses Petits traités I : « J’écris : 1. J’ai envie de me taire » a parlé un peu de lui à diverses occasions. En voici quelques extraits.
— Où avez-vous fait vos études universitaires ?
— J’ai fait mes études universitaires à l’université de Nanterre. J’ai commencé la rédaction, sous la direction d’Emmanuel Levinas, d’une thèse qu’il avait lui-même intitulée « Le statut du langage dans la pensée de Henri Bergson. »
— Avez-vous achevé ce travail avec Emmanuel Levinas ?
— Je n’y ai même pas pensé.
— L’avez-vous commencé ?
— Même pas. Le lien que j’avais avec Emmanuel Levinas était plus profond que ce travail. Les mois de mars, avril, mai, juin 1968 ont balayé d’un coup ce désir d’enseignement. Je m’étais résolu à reprendre l’orgue familial d’Ancenis, où une de mes grand-tantes venait de mourir.
Pascal Quignard le solitaire, Rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison, Éd. Flohic, 2001
Mai 68 lui a infligé une profonde blessure. Après son départ pour Paris, il a fini par brûler plus de mille de ses sculptures composées de divers matériaux : tissus, bois, canevas, papier kraft, verre, et sur lesquelles il avait écrit. Et ce n’est pas tout : il a non seulement brûlé les petits morceaux pour trio ou les sonates qu’il avait composés devant l’orgue ou le piano à Ancenis, mais aussi les carnets de notes qui contenaient les petites histoires ou encore les confessions qu’il avait écrites dans cette maison.
Puis il s’est à nouveau tourné vers l’orgue de l’église d’Ancenis. Il était à l’orgue tous les matins et consacrait ses après-midis à écrire un essai sur l’amour d’après une œuvre de Maurice Scève. Une fois son manuscrit achevé, il l’a envoyé à Gallimard sans l’adresser à personne en particulier. Son essai a attiré l’œil de Louis-René des Forêts, membre du comité de lecture de cette maison d’édition. Louis-René des Forêts fit revenir Quignard à Paris et lui proposa un poste de lecteur, lui qui n’était encore qu’un jeune homme d’une vingtaine d’années. Il le présenta aux membres de la revue Ephémère qu’il dirigeait. De nombreux écrivains et poètes y apportaient leur contribution : Michel Leiris, Paul Celan, André Du Bouchet, Yves Bonnefoy, Henri Michaux ou encore Pierre Klossowski. Est-ce que cela signifie que ses premiers pas d’écrivain se firent sous le signe de la bénédiction ? J’aimerais que vous lisiez cet extrait pour continuer.
Le mouvement de mai fut balayé en quelques heures. Le général de Gaulle, après avoir pris conseil auprès du général Massu, fit élire l’Assemblée la plus réactionnaire depuis le maréchal Pétain. Marcellin était à la Police. Messmer à la Guerre. Les bombes atomiques françaises explosaient à Mururoa.
Nos dieux se mirent brusquement à mourir.
Celan se suicida : ce fut Sarah qui me l’apprit postée dans l’encadrement de la porte de l’appartement d’André du Bouchet.
Rothko se suicida : ce fut Raquel qui me l’apprit dans l’atelier de Malakoff.
(…)
Dans la forêt aventureuse je ne trouvai pas de fontaine, de clairière, de cerf blanc, de charrette, de lance, de reine : mais une dépression, une dépression, une dépression, une dépression.
Écrits de l’éphémère, Galilée, 2005.
Selon Quignard, ce fut la fin de la France d’après-guerre. On retrouve ici le regard qui veille sur le XVIIe siècle, tout comme celui qui observe l’Empire de Rome.
Et vingt-quatre ans plus tard, en 1994, il démissionna sans crier gare de son poste de lecteur qu’il avait longtemps occupé chez Gallimard. Il rompit également les liens avec sa famille. Un peu comme si, à la fin du compte, il avait fini par tout brûler.
L’idée de ne rien laisser après soi m’habite vraiment — même si c’est directement contradictoire avec le fait de publier des livres. Partir aussi nu qu’à l’instant de l’arrivée, c’est un rêve. (…) Manuscrits, lettres, photographies, livres, partitions, dessins, articles, tout s’y enflamme du jour au lendemain tout à trac. C’est si beau quand c’est vous qui brûlez. Remy dit à Clovis : Incende quod adorasti. Cet ordre est si étrange. L’évêque dit au premier roi de France : Brûle ce que tu aimes.
Pascal Quignard le solitaire, Rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison, Éd. Flohic, 2001
En octobre de l’année dernière, je lui ai rendu visite dans son appartement rue Manin, à Paris. Lorsque j’ai pénétré dans son bureau-bibliothèque, mon regard a été attiré par les partitions posées sur le pupitre du clavier. Messiaen, Beethoven, Oiseaux furent les quelques mots que je pus saisir.
— C’est quoi, ça ? lui ai-je alors demandé.
— Je mixe deux musiques ensemble.
— Messiaen et Beethoven ?
— Oui.
Dans les affaires laissées par mon défunt ami de Fukushima, il y avait un carton rempli de disques. Et parmi eux, un album de Messiaen. Le Quatuor pour la Fin du temps. Je l’avais emporté avec moi. Quarante ans après, je n’avais toujours pas posé l’aiguille du tourne-disque dessus.
Au moment de nous séparer, je lui ai dit :
—J’ai perdu de nombreux amis. C’est pour cette raison que je me dois de survivre.
— C’est la même chose pour moi, m’a-t-il répondu.
Un tableau peint par son ami était suspendu dans le hall d’entrée.
Voici la liste des livres de Pascal Quignard traduits en japonais :
Tous les matins du monde, Gallimard, 1991
La leçon de musique, Hachette, 1987
Le salon du Wurtemberg, Gallimard, 1986
Les escaliers de Chambord, Gallimard, 1989
Albucius, POL, 1990
L’occupation Américaine, Éditions du Seuil, 1994
La Haine de la musique, Calmann-Levy, 1996 ; Folio, 1997
Le Nom sur le bout de la langue, POL, 1993
La Frontière, Chandeigne, 1992 ; Folio-Gallimard, 1994
Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia, Gallimard, 1984
Terrasse à Rome, Gallimard, 2000
Les Ombres errantes, Grasset, 2002
Villa Amalia, Gallimard, 2006
Vie secrète, Gallimard, 1997 ; Folio-Gallimard, 1999
Sur le jadis, Grasset, 2002
Les Solidarités mystérieuses, Gallimard, 2011
J’aimerais, pour conclure, exprimer ma profonde gratitude envers Yô Kaji des éditions Kajikasha, grâce à qui ce livre a pu voir le jour. Je tiens également à dédier la traduction de cette œuvre à toutes les personnes victimes de ce grand tremblement de terre, et à tous les habitants de Kumamoto qui ont miraculeusement su se relever.
Kei Takahashi, janvier 2017
Traduction : Déborah Pierret Watanabe