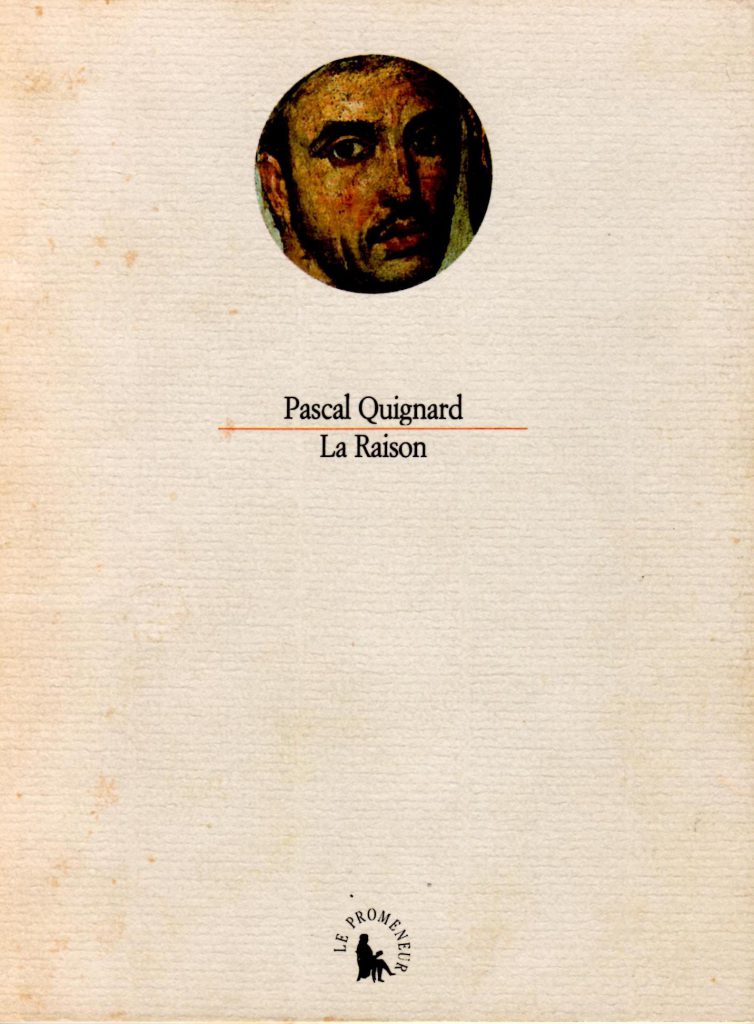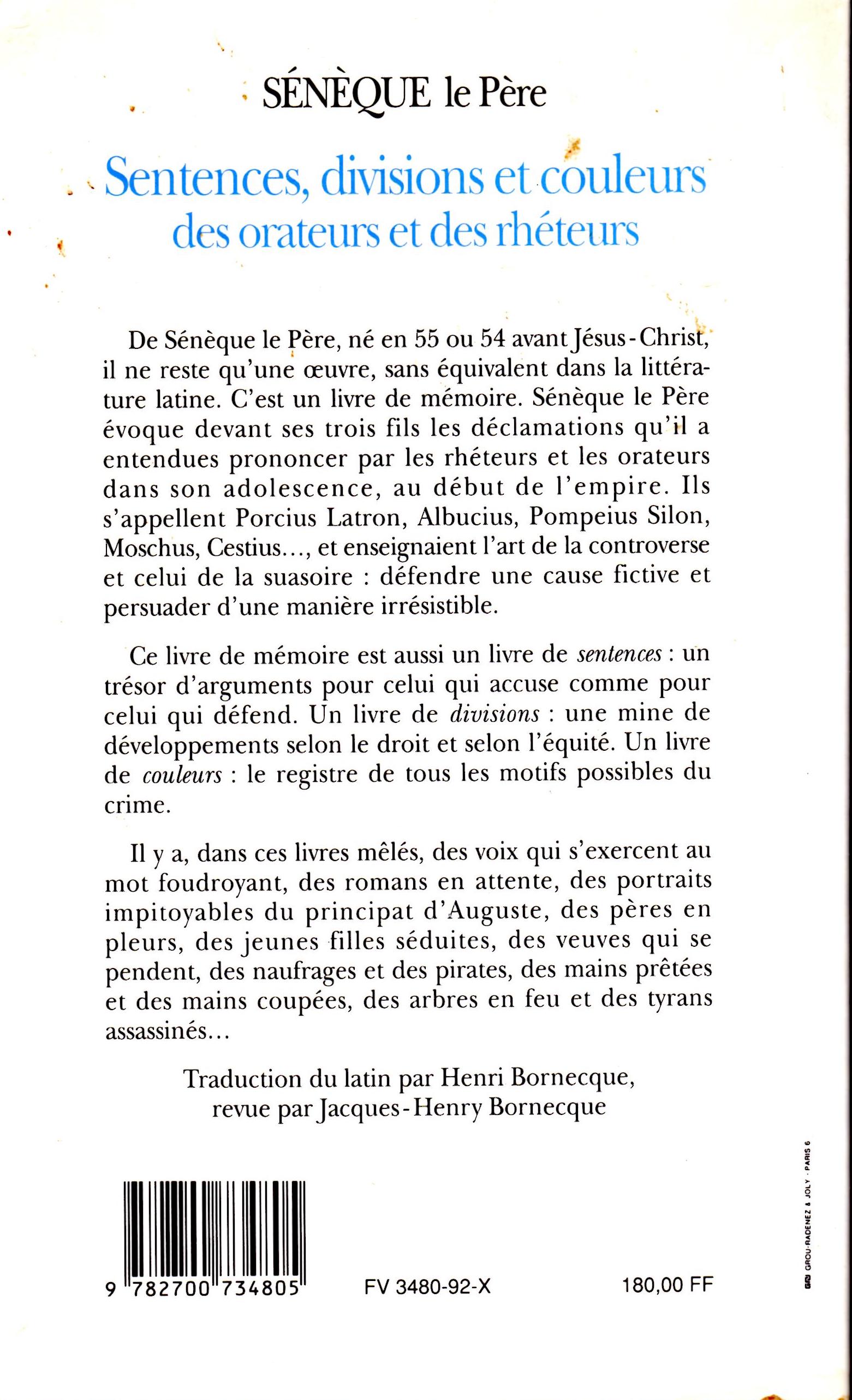
第七章
ラトロは軟弱とギリシア文化と音楽と神々と砂糖が嫌いだった。酸味の強い葡萄酒を好み、これに蜂蜜や固めた雪を混ぜたりせず、そのまま土のなかに埋めて保存した。彼は訪問者を受けつけなくなっていた。口数はだんだん少なくなった。岸辺にたたずみ、雲と藺草と砂埃と花々にかこまれて暮らした。手を前に差しだし、沈黙を聴衆とすることを好んだ。沈黙はとりわけ静かな岸辺の一角に宿ったようだ。一千歩{マイル}先からも、女が機を織る音が聞こえてきた。二千歩先からも、犬がローマの門で吠えたてているのが聞こえた。石斑魚{うぐい}や川梭魚{かわかます}が川面を尾鰭でたたいたり、獲物に襲いかかる音がまるで大音響のように伝わってきた。鴎の鳴き声、蛙の喉を鳴らす声、黄昏の大気にほのかに広がる血、それらすべてがあいまって、野のはずれに、ポルキウスの土手に、尋常ならざる緊迫感をもたらすのだった。井戸はなかった。彼は川に近づいていく。ぬかるんだ土にひざまずくと、川の水を手で掬い、ティベリスの恵みをいただくのだった。彼は一本のポプラを誇りにし、それを大切にした。川辺にのびる木陰は淡く、かぼそかったが、夕暮れどきの焼けつく残照を男一人さえぎるには十分だった。ポルキウスはその影に滑りこみ、夜が降りてくるのを待つのが好きだった。彼はこう言っている。「流れるこの黄色い水、このポプラ、飛び跳ねる蛙、獲物をねらう石斑魚、遠くで犬の吠える声、葉むらのつくる陰に金色のしずくを飛ばしながら水浴びする子供の歓声、川に浸している私の足。幸福がやってくると、言葉は際限がなくなる。意味もなくなり、終わりもなくなる。」
セネカによると、彼は日に二回は黄色と緑の葦の原に分けいって裸になり、水に浸かるとまるで子供のようにはしゃいだという。ティベリスの川面で性器をこすり、そそりたった男根を暗い水面に映して遊んだ。彼は言う、思い出に浴みすると、風景は変わらないのに、皮膚だけが勃起させた後で縮こまった男の性器のように皺寄る、と。そして「思い出は真実ではない。贈り物なのだ」と語った。さらには「男の想いは太陽に見られると、そこで止まる」とも語った。セネカはこう伝えている。「精神の業績にポルキウス・ラトロは大きな尊敬の念を抱いていた。だが彼は、書物や建築やフレスコ画にもまして、理にかなった論述こそ市民の賞賛を得るにもっともふさわしものだと考えていた。」彼は、合理性はつねにその起源の影を引きずっていると言い、その起源を狩人の戦術と比較していた。精神にしろ、その業績にしろ、彼にとってはたんなる自然のかけらでしかなく、それをその他たくさんの枝や葉にまぎれて見えない一本の枝にたとえた。理性など、樹木全体から見れば複雑に入り組んだ血なまぐさい若芽にすぎなかった。思考や都市の秩序にしろ、その都市の住人の風俗にしろ、それ自体がすでに理屈であり、かりそめのものにすぎなかった。ポルキウスいわく、幼年期に頭脳のなかで芽生えたものは自立していないちっぽけなものだ。成熟すると、それはもつれた髪の結び目のようなものとなり、やがてあらゆる種類のより糸や布地をつぎあわせた絨毯となる。たとえば、季節や眠りや消化や家庭や都市や時代など、絨毯はそこから大いにその力ないしは図柄を引き出しているのだ。彼は言う。「理性など、歯や舌や唾が果たすさまざまな役割に比べれば、何の利点も何の豊かさもない。」さらには「竪琴や幾何学のコンパスや、もしaであるならばbであるというような公式をから成り立つ弁証を見ていると、ああ、これらの物はなんと切ないのだろうと思い、感動で涙が出てくる」とも。彼はまたこう考えた。数々の街から成り立つ帝国は、ときおり大気のなかに無用の蜃気楼となってわきあがる蒸気を土台にしている。時間に流れがあり、空間に方向があり、人間の命に必然があり、宇宙に定めがあり、流れる血に大義があるというのなら、無限には顎があろう! 彼は言う、影が集まってできた反映にすぎないこの帝国で、思想が無私の認識であると信じている人々にはどれだけ自分がその無私にこだわっているかがわからないのだ、と。彼は言う。「すべては子供や鵞鳥や木々や女たちの足もとを歩む影なのだ、船乗りの行く酒場を通り過ぎる影なのだ。私は人々を見ているのでも色を見ているのでもなく、それにつきそう茶色に揺らめく斑点を見ているのだ。私は道の石や砂の上を、その道に沿って生い茂る草や麦穂の上を静かに歩んでゆく影の足音を聞いているのだ。毎日、太陽が強い光から淡い光へと移ろってゆくにしたがって影が長く伸びてゆくさまは、目のうえを移動する角膜の斑痕のようだ。かつて私はティベリスのほとりをよく歩いたものだった。ティベリスはローマを流れる川だった。ローマは街だった。君は憶えているか、岸辺で揺れる昆虫のように小さい漁師の網を。小指よりも小さい八人から十人くらいの漁師たちが、肩から灰色の影を落としながらゆっくりと黄色い川のなかに入ってゆく。さらに遠くでは、まるで銅の手鏡の上のぼんやりとした反映のように雲の垂れこめるオスティアの河口の霧にまぎれ、仲間に遅れた引き網舟がひとつふたつ、迫りくる夕闇のなかを帰ってくる。私のすぐ目の前には鵞鳥が列をなして歩いていた。全身がほとんど黄色に染まり、赤く縁どられた鵞鳥だ。ティベリスと冥府のアケロンはひとつの川だったのかもしれないし、どの川も女の子宮にたくわえられている羊水に似ているのかもしれないし、あるいはまた、われわれの身体はこの岸辺に輝く光や足もとからのびる影に包まれているが、それとは別の岸辺もあるのではなかろうか。なにもかもが赤い。川の浮橋の手すりに乗せた私の手も夕日に染まって赤い。たぶん私の顔も赤いだろう。だが、なにひとつ私の顔を見ているものはない。」
第八章
妻が死んだとき、彼はエジプトの商人から小さな皮張りの太鼓を買った。それをたたき、鬨の声をあげた。その後から子供たちが続き、笑い、踊った。アウグストゥスは彼を含めた十人ほどの雄弁家を自宅に招いた。そのとき彼の頭はすでにがたついていたようだ。がたつく deglinguer の語源である declinquer は北海の船乗りが使っていた古い言葉である。船の外板 clin をはずすということで、沈没しそうになることも意味した。さて、この面接と弁論コンクールがどのような次第になったのかは定かでない。アンナエウス・セネカもこの点については何も伝えていない。いずれにせよ、皇帝が帝都からただちに立ち去るように命じたことだけは事実である。
前九年、勅命を受けたアンナエウス・セネカはスペインから友人を迎えにやってきた。ポルキウス・ラトロは自分の小屋もポプラも川原も石斑魚{うぐい}も捨てようとしなかった。縄で縛るしかなかった。愛馬に彼を乗せると、手を荷物に縛りつけた。彼は赤土の故郷に連れ戻された。コルドバの街とグアダルキビル川をふたたび目にすることになった。一行を乗せたガレー船はナルボンヌの港からマジョルカ島のパルマを経て、マラガの港に入った。航海の途中、彼は魚の空揚げと水に浸した小量の乾パンしか食べなかった。スペインの土を踏みしめたとき、彼は川辺か海辺に住まわせてくれと請うた。
第九章
晩年の五年間、コルドバから八マイル離れたセネカの領地のはずれの森でひとり暮らした。片目を失ったにもかかわらず、なお狩りをし、魚を釣った。彼はせきこむようになったが、それは日に二回は水浴びをしたいという欲求に勝てなかったからだった。山から流れてくる川の水は身を切るほど冷たかった。ある冬の朝、鹿を追って丘陵をくだる早瀬を渡ろうとして、ふとしたはずみに胸もとまで水に浸かった。だが、服も羊毛の肩掛けも乾かさず、水がしたたり落ちるままにした。山あいの切り立った道に入ったとき、彼は切り株につながれた山羊にでくわした。山羊はじっとあたりを見まわしていた。そして不気味な鳴き声をあげた。彼はその鳴き声に聞き入り、戦慄した。彼はこのときひいた風邪から快復することはなかった。少なくとも息子のセネカ(哲学者)がポルキウス・ラトロの死にまつわる事情を語るに際しては、そのように言っている。
裏の畑には菰{まこも}を植えていた。菰は大量の水を必要とする植物で、彼はこの実を挽いて粉にしていた。彼は言う、「せめてわが言葉の生き延びんことを!」と。家の前を通りかかる牛飼いたち、あるいはひと碗の乳や藁束を求めて訪れる猟師たちにはこう言った。「箪笥を欲しがり、相手を説き伏せるための理論{システム}を欲しがり、女を、箒を欲しがる男には用心しろ!」
ときおり、領地内の酒場に姿をあらわすこともあった。青い李を食べながら賽子遊びに興じた。ある夜、床についた彼は恐ろしい夢を見た。手足を震わせながらセネカの館の使用人にその夢を語った。戦場で死んだ息子が夢にあらわれたと。汗と涙にまみれ、叫び声をあげて彼は目覚めた。だが彼には息子などいなかった。それは前四年のことだった。キリスト紀元前四年、イエス・キリストは飼葉桶の中で生まれ、母親は股を血まみれにして藁にうずくまっていた。その場に居合わせたのは、優しい声で鳴く牛と低くいななく驢馬だけだった。場所はヨルダン川西域、エルサレムの南に位置するベツレヘム。ローマ暦では七四九年のことだった。マルクス・ポルキウス・ラトロは言う。「この世に人間らしい感情はめったにない。この私でさえ、年に三度か四度しか感じない。だが身の回りにこの気持ちをわかちあえる人はいない。」私はラトロの名のもとに残されている他のどの言葉よりも、これが好きだ。
第十章
アンナエウス・セネカ(ラトロがアウグストゥスの寵を失ったとき、彼をスペインに戻すべく、すべてを託されたのがこの腹心の友だった)が伝える死の経緯は、ことのほか暗い。それは小春日和の暖かい冬の日のことだった。彼は馬で草原に出ると、小さな木立に囲まれた泉に向かった。乗ってきた牝馬から降りると、泉に流れこむ清流で手を、腕を、髭を、刈りあげた頭を洗った。面をあげると、二十歩ほど先でひとりの女がひざまずき、威勢よく石に洗濯ものを打ちつけているのを見かけた。女の口からは生めかしい吐息がもれていた。彼はその隻眼をもっと遠いところ、丘の頂あたりにそらそうとしたが、どうしても視線は若い女のほうに向いてしまうのだった。女は大きな尻をつきだして、トゥニカやトガを掌でたたいていた。女は彼の誘いに応じ、小屋までついてきた。小屋には、かつてそこに詰めこまれていた科木の匂いがし、部屋は三つあった。灰の匂いも満ちていた。彼は土間にじかに炉を掘り、その上を板一枚でおおっていた。彼は女に鼻を寄せ、その匂いに満足した。女は向かい合って彼の膝に座り、男根の上で腰を上下させて快を得ようとした。彼は八回も九回も長く射精し、それまで経験したことのない悦びを味わった。彼は少年期を過ぎたころ、ある年増女とこんなふうにして性を交わしたことがあったが、その名前を思い出すことができなかった。彼は女に金を払い、家族のことを尋ねた。彼女はオスク人だった。彼は女にしばらく一緒に暮らさないかと持ちかけ、その代価として馬を与えることで二人は合意した。女は二人が寝る部屋でほとんどの時を過ごした。部屋の戸口からはそれまで染みついていた匂いとは別の匂いが漂いはじめた。それは重くて甘く粘っこい匂いで、それを嗅ぐと彼はたちまち勃起した。女の汗が発散する酸っぱい匂いも気に入っていた。女はもの静かだった。女はヒヤシンスが好きだった。ヒヤシンスの小さな釣り鐘の形をした花が好きだった。二日目の夜、彼は女の背中をかかえるようにして眠りにつくと、女は彼の性器を尻の間にはさみこんだ。彼は孤独が自分から立ち去ったと感じた。これは夢にちがいないと思った。そして、このオスク女と同じように振る舞ったあの年増女の名前が思い出せなかったことで、自分の人並はずれた記憶力も去っていったのだと思った。女が眠ってしまうと、彼はランプのほの明かりのなかで、女の乳房を見つめ、それに触れ、指先で柔らかな感触を味わった。セネカは、まだあと二つラトロの言葉を伝えている。彼は快楽の後には必ず、大きな炉部屋の壁にかけてある鏡に向かう習慣があった。彼は顔の傷痕とつぶれた目と白い眉を見つめながら、こうつぶやく。「なぜに裏切る、不意の涙よ」〔原註4〕彼が「涙」という言葉で何を言おうとしたのか、よくわからない。だが、誰に聞いてもそれはわからないだろう。彼は死が近づいた最晩年の日々、セネカにこう語ったという。「なぜしゃべる。唇を開けば歯が寒いではないか。」彼は前四年の冬に死んだ。性器はまだ湿っていたが、先端はすでにしぼんでいた。彼は銅鏡に己の姿を映した。その隻眼に幸福のきらめきが見えた。彼は喉をすっぱりと切り裂いた。血がごぼごぼと音をたてて噴き出した。オスクの女はもらった馬に乗って逃げ、その行方は知れなかった。(了)
*4)ミュレル(Mueller)の校訂したテクストは意味をなさない。むしろ《Quid me intempestivae proditis lacrimae?》(Pourquoi me trahissez-vous, larmes inopportunes? なぜに裏切る、不意の涙よ)と読みたい。